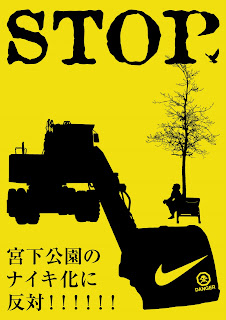■梅雨、6月の誕生花バラの季節。毎年、この時期になると思い出す歌はこれ、「My Favourite Things」だ。
〈バラの上の雨露と子猫のひげ。ピカピカのヤカンとぬくぬくのミトン。ひものついてる茶色の包み。クリーム色したポニーとパリパリのリンゴパイ。ドアの鐘とそりの鐘と子牛のシュニッツェルとヌードル。月を背に飛んでくガチョウたち。青いサシェをつけた白いドレスのおんなの子。鼻とまつげにとまった雪のひとひら。白銀の冬が春に溶けていく頃。これがわたしのお気に入りのほんのいくつか。犬が噛んだり、蜂が刺したり、なんか悲しいとき、お気に入りを思い出してみる。そうしたら悪い気分じゃなくなる。〉
自分で訳すより、チャーミングな音楽、チャーミングなレコードだけを頑固に扱うヴィンテージ・レコード・ショップ:DUCKSOUP (ダックスープ)店長古田くんのブログにいい訳があるので拝借したが、彼の文章には続きがある。ブログともども、是非トップ・ページから店内に入って眺めて欲しい(レコード・プレイヤーなんて持ってないから…という人は、〈SAMPLE〉ページでレコードのジャケットを眺めながらいろいろ試聴するだけでも、うっとり楽しい。『ボリス・ヴィアンのジャズ入門』に出てくるアーティストも大勢聴けます )。
だけどかわいい歌だな。・・・あれ、歌詞に“京都”が入ってないぞ!?
それはともかく、村上春樹『1Q84』の話題で持ち切りのタイミングで、この“Raindrops on roses”の季節がやってきて、頭の中にはジュリー・アンドリュースやジョン・コルトレインのフレイズが鳴り止まなくなった先日、またも『村上朝日堂』が読みたくなった。もう、自分でもおかしいくらい、毎年6月に読むのがほとんど儀式と化している。新作はここしばらく何も読んでいないので全然熱心なハルキストではないオレですが、この『村上朝日堂』だけはそのスタンダード・ナンバーからの連想で、毎年6月に読み返してしまう。それも、いつも“ヌードルを添えたシュニッツェルの話”から。

(・・・全然関係ないことで、かつ全くの私見ですが、村上春樹はアナキストだと思います。オレはあとになって考えると、バクーニンなぞを齧るずっと前の、子供の頃のスナフキン体験と学生のときに読んだ村上が、自分のアナキズム指向の土台にあるように思うのです。だからアナキズムが世界で広く愛されていることも、オレの中では皮膚感覚レヴェルで納得できるのです。熱心なハルキストがみなアナキストかどうかはもちろん別の話ですが)。
で、それは、正確には「ビーフ・カツレツについて」という題のエセーで、内容は有名だから知ってる人も多いと思うけど・・・僕(兵庫で育った村上)は東京に来て好物のビーフ・カツレツを出す店がなかなか見つからなくて困り、次善の策としてウィンナ・シュニッツェルをよく食べている。その“ウィーン風仔牛のカツレツ”は、肉をビール瓶で薄くなるまで叩いてころもをつけ、ひたひたの油で片面ずつ(フライパンで)揚げたもので、その上にレモンの輪切り、その真ん中にはアンチョヴィーで巻いたオリーヴをのせ、上からケッパーも振る。熱いバターをかけ、つけあわせは白いヌードル。これが決まりで、これだけ揃って初めてウィンナ・シュニッツェルである。『サウンド・オブ・ミュージック』の「マイ・フェイヴァリット・シングス」にも「私の好きなものは・・・ヌードルを添えたウィンナ・シュニッツェル」という歌詞が出てくるけれど、そのとおりである。逆に言うと、僕の嫌いなものはヌードルのついていないウィンナ・シュニッツェルということになる・・・という、肝心な部分を要約するとそんな感じだ。
学生時代、アルバイト先で同僚の女の子たちが3人、休憩時間に、「『村上朝日堂』を読んだらヌードルを添えたシュニッツェルが食べたくなった」という話をしていた。実はオレも食ってみたいんだと、社食のサンマーメンを啜りながらオレも話に同意すると、じゃあ4人で手分けしてウィンナ・シュニッツェルの食べられる店を探そうよということになったが、しかしインターネットなどない時代、誰もそう簡単にそんなものを食べさせる店なんて見つけられなかった。そうしているうちに3人の女の子のうちの2人が、女の子同士のいわゆる“ありがちな”問題で仲たがいしてしまい、最初のシュニッツェル・プロジェクトは頓挫した。で、その問題はしばらくの間バイト先に緊張の入り交じったどこやら甘酸っぱい雰囲気を漂わせていて、それは別に不快でなく、最後はちょっと悲しい結末だったのでよく覚えているが、それも6月の話だった。
とにかく、当時から村上人気は絶大だった。で、“砂漠の狐”ロンメル将軍と食堂車の話からビーフ・カツレツを経てシュニッツェルに到るおいしそうな連続エセーを読み、その料理を未体験だった村上ファンは、いつか食べたい料理のリストに《ウィンナ・シュニッツェル》を確実に書き加えたはずだ。
寿司は日本で食べるのがきっと一番なんだろう。ならばウィンナ・シュニッツェルはウィーンで食べるのが一番なはずだ。が、残念なことにウィーンにはまだ行ったことがなく、結局、オレが最初にウィンナ・シュニッツェルを食べたのはブリュッセルでだった。例の女の子たちとの約束から7~8年後の話で、1人でたまたまぶらっと入った横丁のビストロの売りの1つがシュニッツェルだったのだ。うまいベルギー・ビールを飲みながら、夕刻の街並みを眺めながら、食べた。
思い起こすと、それは想定内の、安心な味だった。叩いた仔牛の肉に火が入った、ちょっとふんわりした触感と、かなり細かいパン粉のついたきつね色の衣のサクッとした感じのコントラストが充分おいしいのだが、1つだけハッキリと覚えているのは、一口目で即、これよりも村上春樹の食べてるやつのほうが絶対にうまいはずだ、と思ったことだ。実際に自分で食べている結構なシュニッツェルの味よりも、村上のエセーの中からしてきた想像上の味の方がうまい・・・(ここにはなかなかリアルな人生訓がある)。
そのシュニッツェルは充分に大きく、味もかわいらしく、ビール2杯とともに満腹になったのだが、致命的だったのは、つけ合わせがストンプだったことだ。そのストンプ自体もうまい(ブリュッセル名物だ、確か)し、シュニッツェルと合うのだが、レモンとケッパーはあったものの、アンチョヴィーで巻いたオリーヴもないし、何より肝心のヌードルが添えられていないのだ。その代わり、好きなだけ食べな、と出されるパンも絶品だったのだが、やはり初シュニッツェル体験としては何とも微妙な気分になったものだ。それも6月の末の体験だった。ヨーロッパの6月は気候も最高で、これまで何度も欧州の6月を過ごしてきたが、歌い出しと合わないせいか、あっちでは「マイ・フェイヴァリット・シングス」は見事に頭に浮かんでこない。
今、『ボリス・ヴィアンのジャズ入門』の文字校正をやっていて、“ストンプ”という文字を見たばかりなので、それでもまた、ブリュッセルで食べたシュニッツェルを想い出した。その“踊り/リズム”の方はスペルが違うんだけど、カタカナにすると一緒なので、ジャズ原稿の中に“ストンプ”という文字をみると、ほんのり暖かく、ちょっとだけクリーミーなじゃがいものサラダが食べたくなる。この連想からも、おそらく一生逃れられないだろう。
ちなみに土岐麻子の歌う「マイ・フェイヴァリット・シングス」もいい。“Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles”の部分の発音は、何度聴いても軽やかでまろやかで、村上の方のヌードル添えシュニッツェルの味を想像させます。彼女は最近のいわゆるポップ・チューンも全然悪くないけど、オヤジ・ミュージシャン(本物の父親入り)をバックにしてジャズやスタンダード・ナンバーを歌ってる方が好きだ、という話を『ボリス・ヴィアンのジャズ入門』のデザイナー(前出の古田くん同様、オレの堅気時代・・・輸入レコード屋ですが・・・の同僚)大久と、先日したばかりだった。彼はドイツのジャズ・ギターに関しては世界で指折りの専門家だ。変わったものに興味を持つヤツもいるものだ。